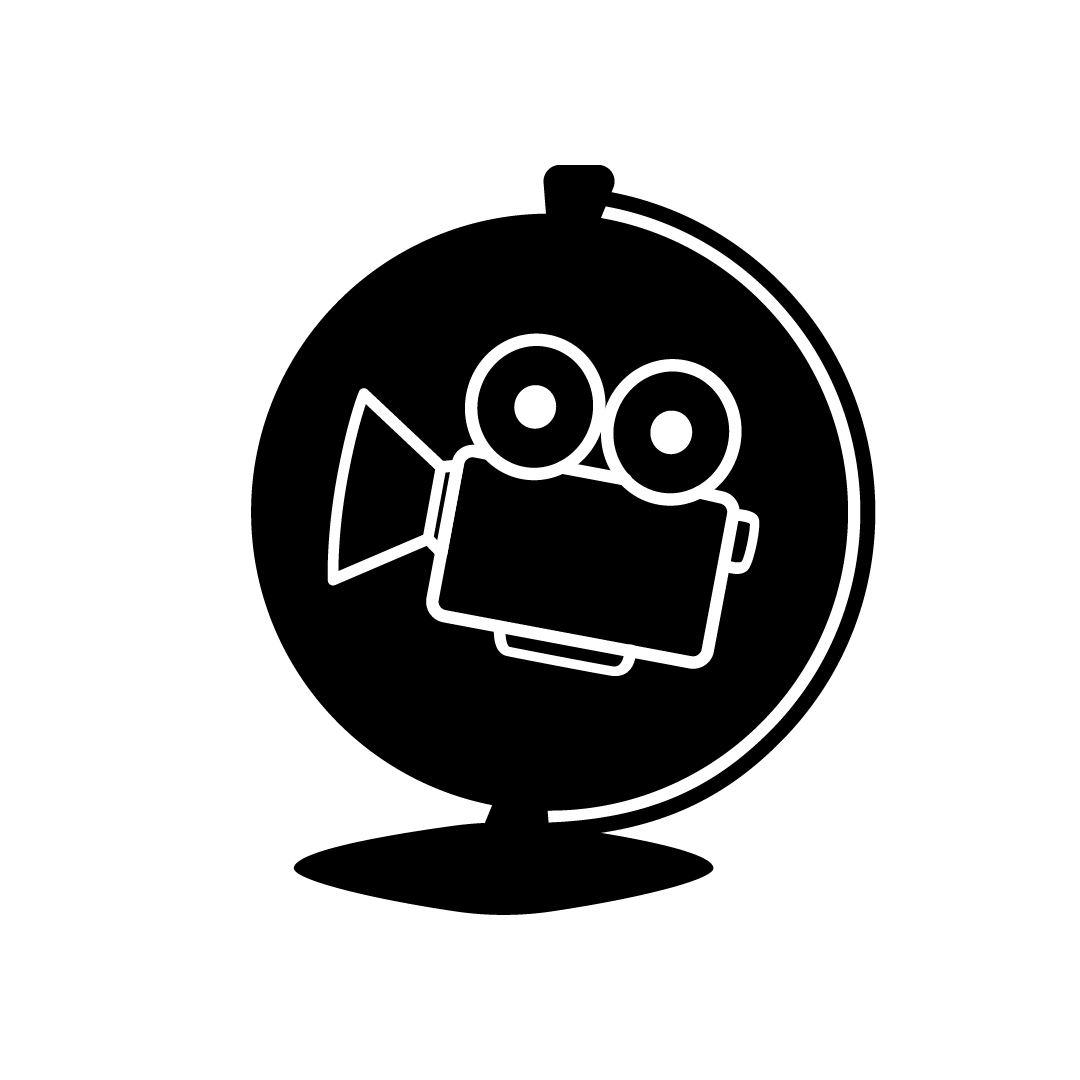デューン
1965年に発表されたフランク・ハーバートの小説『デューン』は、SF小説として最も影響力のある作品のひとつであり、『スター・ウォーズ』をはじめとする代表的なSF映画にも影響を与えた。スターウォーズもその一つだ。しかし、「デューン」そのものを映画化する試みは、必ずしも計画通りに進んできたとは言えない。(アレハンドロ・ホドロフスキー(Alejandro Jodorowsky)監督がハーバートの作品を映画化しようとした際のドキュメンタリー『Jodorowsky ''s Dune』を参照)。デヴィッド・リンチの1984年版はカルト的な人気を博したが、公開当時は大失敗と見なされていた。しかし、ドゥニ・ヴィルヌーヴは、『エネミー』『アライバル』『ブレードランナー 2049』で見られたように、異なるタイプの映画監督である。彼の映画作りに対する小説的なアプローチは、他の映画監督が失敗したところで成功し、複雑すぎるストーリーを消化しやすく、完成度の高い珠玉のSF作品に変えることを可能にしたのです。そのすべてが『デューン』に反映されている。この壮大な映画は、見事であると同時にスマートであることに成功しており、今後もその傾向は続くだろう。
スペンサー
2016年のオスカーにノミネートされた『ジャッキー』と同様に、パブロ・ラライン監督は、誰もが知っているが、理解している人はほとんどいないと思われる象徴的な女性を、『スペンサー』でまた親密に描き出したのだ。クリステン・スチュワートは、(チャールズ皇太子の妻として、また王室の一員として)期待されることを行い、自分の主体性を維持するという境界線をまたごうとする役柄に変身している--一方で、チャールズは不倫をしており、愛人に買ったのと同じ真珠の紐まで彼女に買っていることを十分に知っているのだ。この映画では、真実は伏せられているが、ダイアナが結婚した先の王室という組織に追い詰められ、力不足を感じているという全体の心情は、彼女の個人的な苦悩を知る私たちには真実味を帯びているように思われる。この映画は、ダイアナとチャールズが正式に別れる1年前、そしてダイアナが早すぎる死を迎える6年前の1991年を舞台にしている。
カードカウンター
オスカー・アイザックが演じるウィリアム・テルは、過去に問題を抱えた退役軍人だが、ギャンブルの世界に没頭することで忘れようと最善を尽くし、ブラックジャックやポーカーのトーナメントで全米を旅している。その道中、彼はCirk(Tye Sheridan)という青年に出会い、親しくなる。彼は軍の大佐(Willem Dafoe)に復讐するために、ウィリアムの助けを求めるのだった。ウィリアムは、カークから自分の境遇や計画を聞かされ、カークとの関係が贖罪のチャンスになるのではと考えざるを得なくなる。この映画は、ポール・シュレイダーが脚本と監督を担当し、シュレイダーの多くの主人公が直面してきたのと同じ罪と贖罪の脚本で主に演じられています。しかし、『カード・カウンター』は、シュレイダーのキャラクターが純粋に贖罪に関心を持っているように見える数少ない作品の一つであるように感じられる。
ドライブ・マイ・カー
まずはじめに:そう、『Drive My Car』は3時間の長編映画だ。しかし、この点については我々を信頼してほしい。濱口竜介が脚本と監督を務めたこの映画は、妻を亡くして2年後、広島で2ヶ月間の舞台演出のレジデンスを引き受けた劇団員、加福祐介(西島秀俊)の物語である。毎日1時間かけて劇場を往復する彼は、運転手を任された若い女性(三浦東子)と徐々に友情を育んでいく。彼は、キャストやスタッフとの問題や、いまだに心に残る妻への裏切りを打ち明けるのだった。ドライブ・マイ・カー』はロードムービーであり、景色を楽しむための映画である。オンラインではまだご覧いただけません。
パス
ハーレム・ルネッサンス期の作家ネラ・ラーセンの1929年の小説を、『GODZILLA vs. KONG』のレベッカ・ホールが初監督した。リーニーは医者(アンドレ・ホランド)と結婚し、ハーレムの高級住宅に家族で住んでいる。一方、クレアの夫は実業家(アレキサンダー・スカルスゲルド)で、人種差別主義者であり、肌の色が白いため、妻が黒人であることに気づいていない。この映画は、華麗な想像力と美しい演技で、人種に関する力強い声明を出しており、今日でも反響を呼んでいる。
緑の騎士
デヴ・パテルが、『Miss Juneteenth』の脚本家デヴィッド・ロウリー監督のもと、新しいタイプのアーサー王伝説を描き出す。アーサー王の甥で難病のガウェイン卿を演じるパテルは、緑の騎士に立ち向かう旅に志願し、命を賭けている。危険な任務だが、特権階級のガウェインは、大胆不敵な戦士としての地位を確立しようと決意する。アーサー王伝説の脚本に忠実でありながら、ローリーは「帰ってきた英雄」という図式を覆すような軽快な演出を躊躇なく行っている。
ロスト・ドーター
オスカーにノミネートされたマギー・ギレンホールは、2021年にエレナ・フェランテの小説を映画化した『The Lost Daughter』で見事な監督デビューを果たした俳優であり、ギレンホールはこの作品でも脚本を担当している。本作の素晴らしさの多くは、ギリシャで休暇を過ごす文学教授のレダ(オリヴィア・コールマン)が、子育てに追われることがあると認める若い母親ニーナ(ダコタ・ジョンソン)と親しくなる際の、常に感じる不安感にある。レダは自分の過去をあまり語らずに、ニーナに「わかるよ」と言う。しかし、彼女たちはギリシャのビーチサイドに座っていても、常に壁が迫っているように感じ、いつ何か恐ろしいことが起きてもおかしくない状態です。この映画は、観客の頭の中に入り込み、そこに留まる方法を理解しているギレンホールの証しである。
リコリスピザ
ポール・トーマス・アンダーソンは、現在活躍している監督の中で最も多彩なフィルモグラフィーを持つ監督かもしれません。四半世紀前の1996年に『ハードエイト』を発表して以来、彼はポルノビジネスの是非を描いた『ブギーナイツ』、子供時代の約束と大人になってからの現実の間でしばしば見られる人生の二面性(『マグノリア』)、何よりもお金を大切にする残酷な探鉱者(『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』)、カルト教団の指導者(『ザ・マスター』)、そしてオートクチュールの映画制作を続けてきたのである。また、"崖っぷち "な靴下好きのオートクチュール・デザイナーは、妻から死の淵に追いやられるのを楽しんでいた(『ファントム・スレッド』)。 といった具合だ。
アンダーソン監督の作品には、次にどのような題材が登場するかという予測不可能性がありますが、通常、アンダーソン監督の映画には2つのことが期待できます。1970年代、サンフェルナンド・バレーで育ったアンダーソン監督が、カリフォルニアの太陽を浴びながら、子供時代や初恋を描いた作品だ。(故フィリップ・シーモア・ホフマンの息子であるクーパー・ホフマンの起用は、感動的な天才の一撃であった。
犬の力
ジェーン・カンピオンは12年ぶりに長編映画の撮影に戻り、『The Power of the Dog』でリベンジを果たした。ベネディクト・カンバーバッチは、悪役のフィル・バーバンクを演じて、タイプに反した演技をすることが期待されています。そのため、この作品では、「崖の上のポニョ」と呼ばれる。ジョージが労働者階級の未亡人ローズ(キルスティン・ダンスト)と結婚し、一緒に暮らすために彼女を家に連れてきたとき、フィルはあらゆる場面で彼女を苦しめることを楽しんでいるように見える。しかし、彼女の息子ピーター(Kodi Smit-McPhee)が夏休みを一緒に過ごすようになると、フィルは徐々にこの若者を自分の支配下に置くようになるようだ。しかし、フィルが持つ脅威的な性質には、隠された、しかしもっと弱い、もう一つの側面があることは言うまでもない。