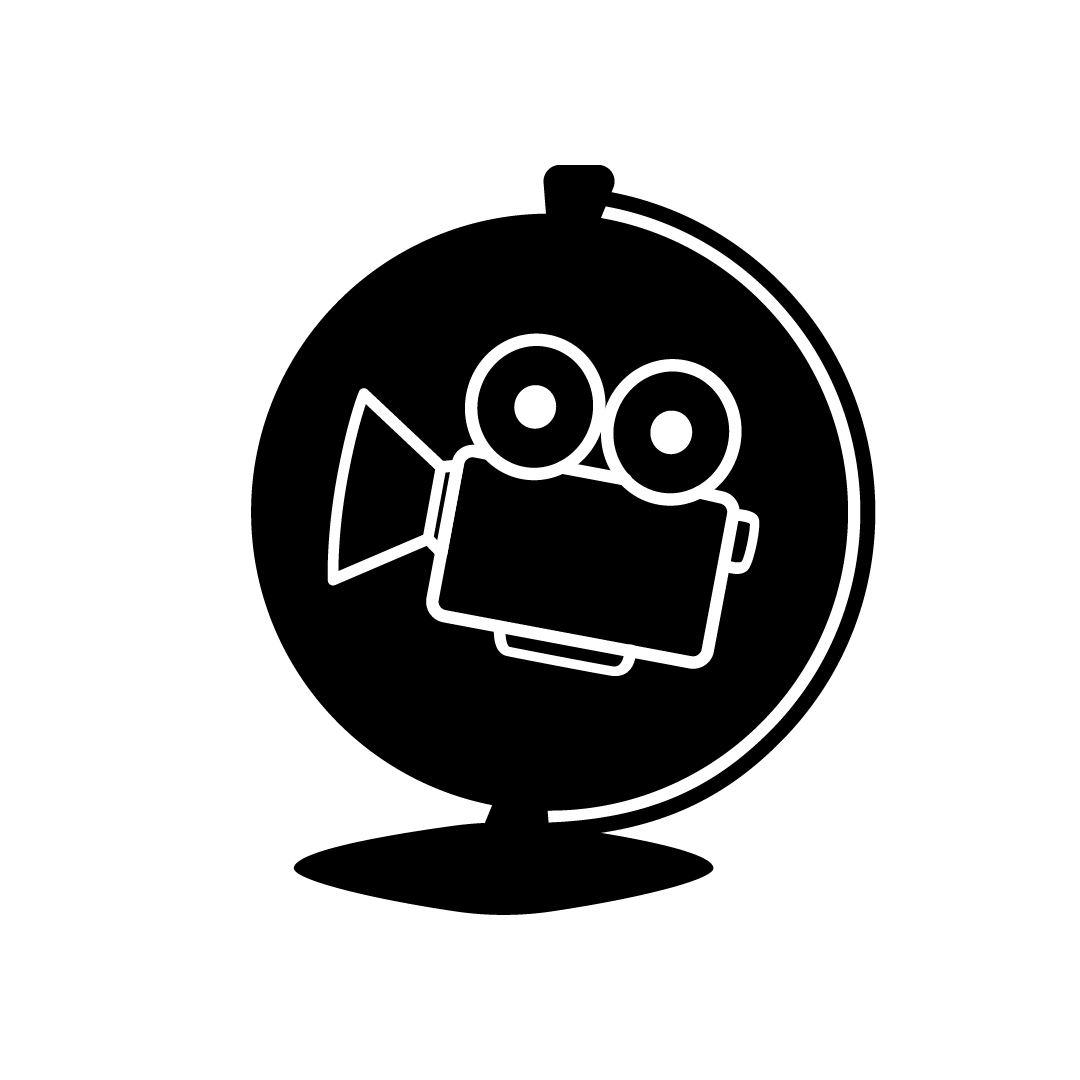普通の映画ではありえないほど多くのうなずきやウィンクが散りばめられた『The Unbearable Weight of Massive Talent』は、メタナラティブという概念を限界まで押し進めようとする作品である。この作品でニコラス・ケイジは、ニック・ケイジと名乗る架空の自分を演じ、自分が出演する映画の脚本を書くようにと頼まれる。しかし、これほど長く、愛情を込めて自分のへそを見つめた芸術作品はないと思われた矢先、この作品は映画そのものへの賛歌であり、実はニコラス・ケイジのことではないことが明らかになる。
話を戻そう。マッシブ・タレント』では、ニック・ケイジは不満があり、経済的に破綻寸前で、一世一代の大役を逃したところだった。キャリアへの執着が元妻と娘を遠ざけ、若き日のニッキーの幻影に苦しめられている。自暴自棄になった彼は、ペドロ・パスカル演じる金持ちのスーパーファン、ハビの誕生日パーティーに参加するために100万ドルを受け入れる。これは、現実のケイジとは対照的だ。彼は結婚して2人の息子を持ち、おそらく若い頃の自分の幻影に悩まされることはないだろう。(1990年に受けたインタビューによると、ニッキーは「不愉快で、傲慢で、不遜だった」と語っている。 「また、クレジットにはニッキー役がニコラス・キム・コッポラ(ケイジの本名)と記載されており、余計に混乱させる。
この映画自体の前提の耐え難い重さを考えれば、『Massive Talent』がどのように破綻したかは容易に想像がつくだろう。しかし、そうはならなかった。それどころか、ニック・ケイジを使ってニック・ケイジをからかうことだけを考えた一本調子の映画になりかけたところで、ひねりが加えられている。ハビがニック・ケイジに、『ナショナル・トレジャー』のポスターや『フェイス』などのニッケル・ケージ・グッズを見せる。
この映画の真骨頂は、その参考文献に表れている。バナナの皮を被ったニック・ケイジや、ケイジのサタデー・ナイト・ライブ出演といったミーム的な内容への言及は、どこにもない。代わりにMassive Talentは、『マンディ』のチェーンソー、2018年に公開されたケイジの驚くほど豪華な実験映画、そしてケイジの象徴的な " Not the bees! " のセリフは『ウィッカーマン』から。また、多くのシークエンスがこの俳優のフィルモグラフィからそのまま持ち出され、瞬間やシーンが忠実に再現されているが、ケイジという人物に具体的に言及することは比較的少ない。映画が主役なのだ。
ハーヴィは、ひいてはこの映画自体も、ケイジの風変わりな名言の数々を偶像化しようとするものではない。魅力的なのは、そもそもこの俳優がその瞬間を観客が感じるものにすることに成功している点だ。ハーヴィも映画も、「バカバカしい」とか「非現実的」といったことにとらわれず、奔放な情熱で本物の感情や経験をいかにしてとらえるか、ということに心を奪われている。結局のところ、すべての感情や経験が、ハリウッドの衛生的なパッケージにきれいに収まるわけではないのです。
これこそ、ニック・ケイジがキャリアの大半を費やして追求してきたものである。それはまた、映画そのものの目的でもある。私たちが顔を交換したり、独立宣言書を盗んだりする映画を見るのは、現実的でもっともらしいことがスクリーン上で起こるのを見たいからではありません。私たちが映画を見るのは、印象的なキャラクターと、可能な限り幅広い感情をとらえたシーンがある、カラフルで生き生きとした物語を見るためなのです。
このレンズを通して、ニック・ケイジはニック・ケイジの代用品としてではなく、情熱の代用品として機能する。映画の終わりには、なぜ本物のニックがこれほどまでにキャラクターを分けて考えることにこだわるのかが明らかになる。Massive Talent』はミームの背後にいる人物を尋問しようとするのではなく、むしろ、とんでもない範囲の映画ファンに衝撃を与えた、熱狂を表面化する能力の高い俳優の伝承を掘り下げようとするものだ。そこに、神話が持つインスピレーションを与える力を見出すのだ。ニック・ケイジは、今や風刺の対象となった実在の人物のフォークヒーローであり、映画があり得るものすべてを体現した存在である。