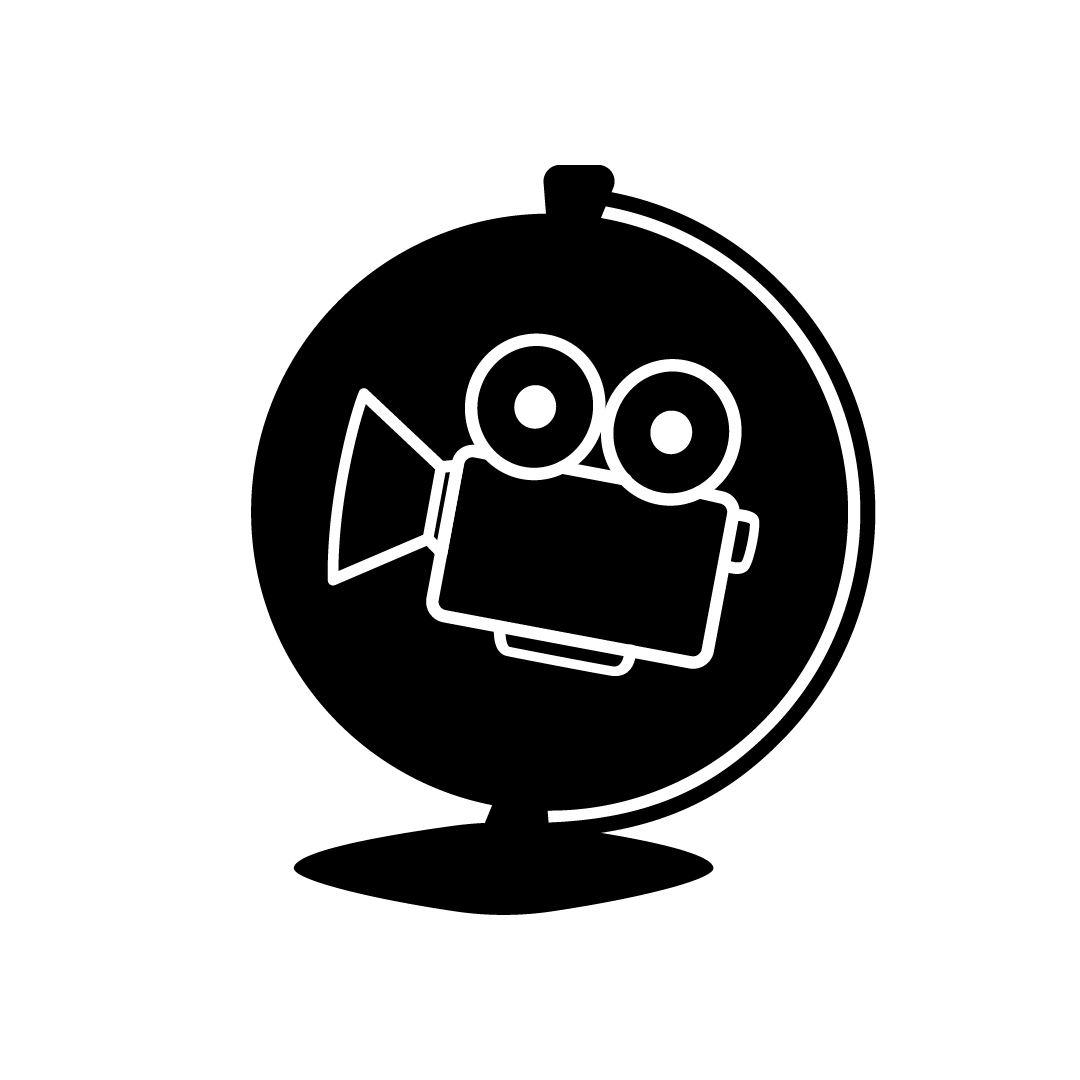社会派スリラーというのは難しい仕事だ。サスペンスとホラーというレンズを通して、抑圧の残酷さを検証し、最も大胆な例では、大胆に疑問を投げかけるという使命を帯びている。このジャンルでは、映画制作者は洞察力とエンターテインメントの微妙なバランスをうまく取ることが要求される。脚本家マリアマ・ディアロによるスタイリッシュで研究熱心なデビュー作『Master』では、このジャンルが真の声を見つけたと言えるでしょう。ニューイングランドの名門大学における黒人としての心理的トラウマを中心に、アメリカにおける人種間の不和が、時に単純に、時に複雑に、しかし常に永続的にもたらす恐怖をむき出しにして、歯がゆい不安を表現している。また、社会派スリラーの限界に目を向け、このジャンルに新たな教訓があるとすれば、それは何なのかを考える上でも喜ばしいことである。
Amazonプライムで公開されたばかりの『Master』は、「国とほぼ同じ歴史を持つ学校」アンキャスターを舞台に、3人の黒人女性の1年間の生活を追ったもので、彼女たちは微差に直面し、刺し、刺激し、ほとんどが白人のエリート大学に入学するという精神戦場を踏破した黒人なら誰もが経験する感情を喚起する。パラノイアと疑いの混ざった感情。混乱に覆われた恐怖。感情的な過負荷による重い痛み。すべてが、そして誰もが、閉ざされていくような感覚。イェール大学出身のDialloは、この領域を注意深く、忍耐強く意識し、リアリズムと、Ta-Nehisi Coatesが「実体のないものの恐怖」と呼ぶ、黒人の生活体験から生じる超自然的な恐怖の間を行き来しながら、探っている。 "
そのため、このような "萌え "要素を取り入れることで、"萌え "要素を取り入れることができるのです。そのため、"萌え "と "癒し "をキーワードに、"癒し "と "癒し "を融合させた新しいライフスタイルを提案する。ゲイルが「マスター」の良心だとすれば、彼女はまさにそうであり、ジャスミンはその感情の中心であり、震える鼓動なのだ。
そんな中、ジャスミンはある民話に心を奪われる。それは、何世紀も前にこのキャンパスで死んだ魔女と思われる女性が、毎年新入生を恐怖に陥れ、キャンパスに出没しているというものだ。1965年、アンキャスター大学初の黒人学生が、ジャスミンのいる同じ部屋でリンチされた。1965年、アンキャスターで初の黒人大学生がジャスミンと同じ部屋でリンチされた。白人対黒人の絞首刑という暴力的な歴史が、撲滅と大衆娯楽の一形態であり、アメリカ独自の「呪い」の1つであることにうなずきながら、ディアロは社会派スリラーを21世紀の怪談に仕上げたのである。
ディアロは、ジャスミンとゲイルを取り巻く闇が深まるのを観客がよりよく理解できるように、様々な美的トリックを駆使している。これは主に、ディアロの特徴である赤が心に訴える色彩、影、そして立体感と奥行きを感じさせる交互のカメラショットの使用によって実現されている。より広く言えば、この映画は、特に高等教育における構造的システムの悪質な性質、つまり、それらがどのように、なぜ、そして誰のために維持されているのかを暴露している。この映画は、権力体制に立ち向かおうとする者は、その追求そのものが呪われることを暗示している。
この映画に対する批判的な問いが第1四半期に訪れるが、終始その輝きを保ち、黒人に焦点を当てた場合、最も魂を揺さぶり、謎めいたものであっても、特定の経験に縛られたままのこのジャンルの本質を照らし出している。ある夜、ジャスミンが部屋に戻ると、彼女はびっくり仰天する。ある夜、ジャスミンが部屋に戻ると、「お前は誰だ? 「と、白人の上級生が尋ねてきた。ジャスミンのルームメイトに招かれた他の学生たちも、すぐに不愉快な返事を返してきて、まるで短剣のように突き刺さる。彼らは、ある種の黒人達成イメージの決まりきった代用品としてよく使われる黒人女性の名前を叫ぶ。ビヨンセ」「リゾ」「ウィリアムズ姉妹の一人」。 "
そして、この時代にはデジタル機器(InstagramからYouTubeまで、私たちが毎日使っているものがたくさんあります)があふれていて、私たちはどう生きるべきか、誰になるべきか、何を目指すべきで何を目指すべきでないかを、嘘と欲とパラドックスで固められた土地で教えてくれるので、鏡に映る自分の姿を認識することが難しくなることもあるのです。自分が本当は何者なのかを知るために。私たちの国は矛盾に縛られているのです。では、何が救いになるのでしょうか。私は、突然の恐怖に直面したとき、真の安定剤となるのは、自己の確信だと思いたいのです。観客は、ジャスミンが足場を固めようとするのを見守るが、その経験は彼女のバランスを崩し、そのアンバランスさ-自分が誰なのか、自分が属しているのか、という疑問-が、この映画が驚くべき結末へとねじ曲がるときに彼女を飲み込んでいくのである。
マスター』は社会派スリラーだが、ホラー作品でもあるため、自己への問いかけに真のテーマの本質を見出している。白人の枠の中で、アメリカの黒人の物語は基本的に恐怖の物語である。そうでないわけがない。そのため、ブラックホラーは人間の解放の限界について正面から取り組んでいる。
しかし、社会派スリラーというジャンルは、階級的不安、人種的不調和、感情的恐怖をリサイクル的に転覆させることで、あまりにもリラックスしすぎてしまったのではないかと思うことがある。ジョーダン・ピールの2017年の大ヒット作『ゲット・アウト』によって復活したこのジャンルは、『ティレル』(2018)や『彼の家』(2020)といった作品を通じてその問いかけを拡大し、ありふれた体験をよりグロテスクでより恐ろしいほどリアルなビジョンに反転させる。そのテーマは時代を超えて関連性があり、社会派スリラー映画--リアリズムを実験しながらも受け入れなければならないジャンル--をどう理解するかの多くを定義しているため、(視覚的ではなく物語的に)可能なことを制限することにもなっているのだ。
アートによって、人種や階級、性別による抑圧の犠牲を他者がより良く理解できるようになることは理解できます。日々、抑圧と向き合っている私たちが、アートによって認識を深めることができるのです。見られていると感じること。それはすべて重要なことです。しかし、実際のところ、黒人にとって、トランスジェンダーの子どもたちにとって、女性にとって、クィアにとって、障害者にとって、常に不利な立場に置かれ、自分たちが問題だと言われるすべての人にとって、生きた現実は常に解釈より優先されます。このジャンルは、私たちがすでに知っていることを伝えることしかできないので、その範囲は限られているのです。
社会派スリラーは、アメリカが謳う進歩に対抗するために必要なものであり、アレゴリーを通じて国家の本質を明らかにする。恐怖は私たちの中に生きている。ニュースで見たり、TikTokで遭遇したりする。黒人の痛みは、今や毎時間、バイラルで流れるように最適化されている。ジャスミンが学んだように、こうした対立は簡単には防げない。そして、幸運にも黄昏時を乗り切ったとしても、肉体的・精神的なダメージは残る。その代償は何だったのか。それは、ゲイルが自分で考えなければならない最後の問いである。