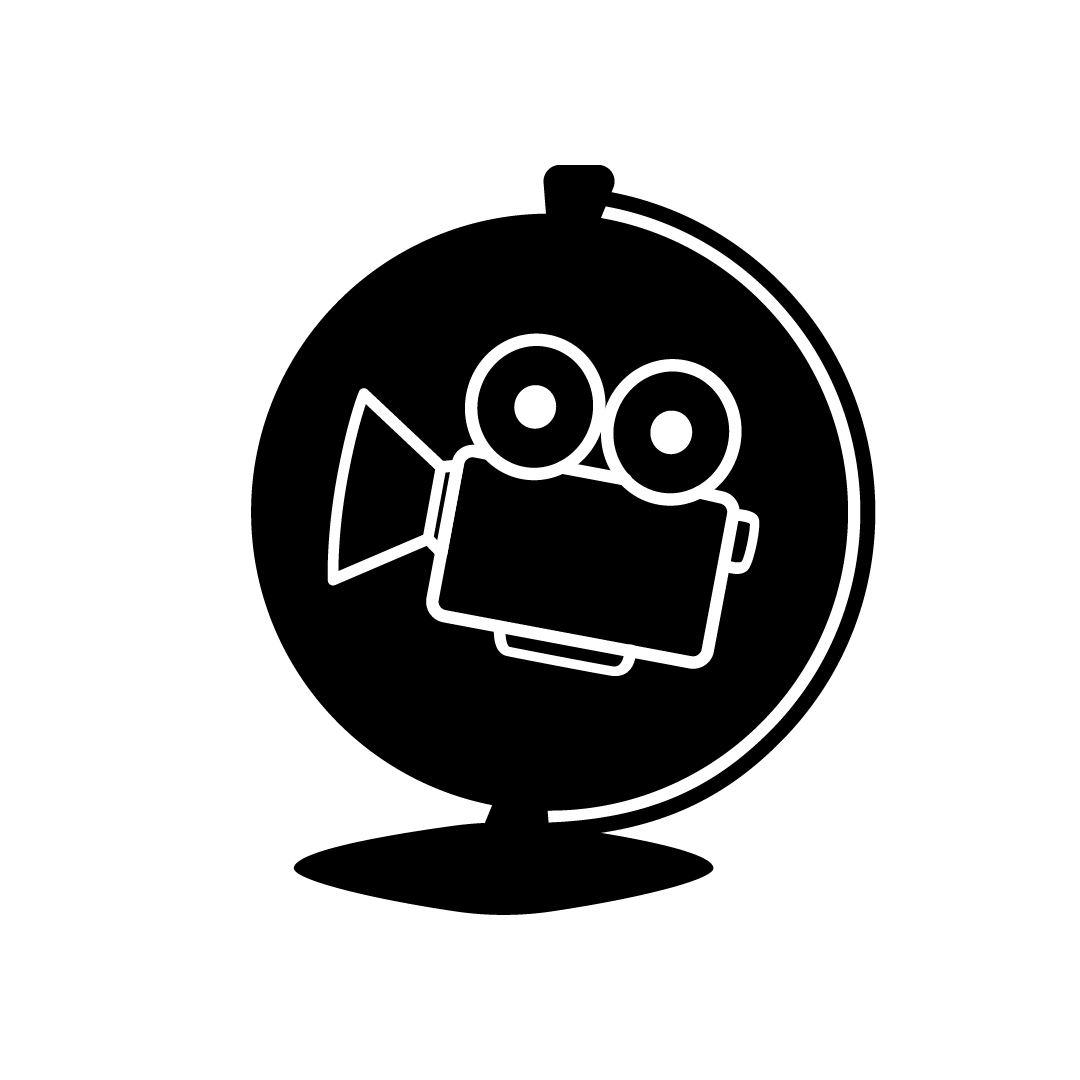SF映画において、世界観の構築ほど重要なものはない。これは、必ずしも宇宙船や遠く離れた惑星の壮大なショットを意味するものではありません。デューン』のような豪華絢爛なスペクタクルがある一方で、特撮の予算が少ない、あるいは存在しない小規模なSF映画もたくさんあるのです。そのような映画では、未来的なビジョンを具体化するために、他の方法を使わなければならない。雰囲気のあるサウンドトラックは、スリリングなムードを作り出すのに大いに役立つ。プライマー』の自作タイムマシンや『ラプシス』の森の中に張り巡らされた量子コンピュータケーブルのような巧みなセットデザインは、最先端のCGIがなくても観客を新しい世界に没入させることができる。登場人物同士の会話の仕方でさえ、トーンを設定する費用対効果の高い方法となり得る。実際、最近の映画では、独特の話し方がフィクションの世界を確立するのに重要な役割を果たす作品がたくさんあるほど、費用対効果は高い。サッドボイスSFとでも呼ぼうか。
震えたり、涙が出そうなほど悲しいわけではありません。anhedonicのように悲しい、情熱を奪われた、落ち込んだ。平坦な感情を表し、時には不自然な拍子記号を伴う。典型的な例です。 この映画は、ロマンチックな相手とうまくいかなかった人々が、自分の好きな動物に変身してしまうというファンタジックなディストピアを舞台にしている。ファレル演じるデビッドは、長年付き合っていた恋人にフラれ、1ヶ月半でソウルメイトを見つけなければならない。ストレスフル! 奇妙な話だ。しかし、彼は無表情で、この奇妙な運命を受け入れている。ロブスターに変身したいんだ、なぜなら、ロブスターは一生、繁殖力が衰えないから。 「この映画でデヴィッドが出会う他の不運な独身男性も、どんな状況に置かれても、硬い単調な声で話す。ランティモスの俳優たちは、非常に感情的な状況にもかかわらず、しばしば無表情であり、それは彼の多くの作品に共通する特徴となっているほどです。ロブスター』では、このギミックが功を奏し、デヴィッドの孤独感、そして彼と他のメンバーがいかにつながりを持つことが難しいかが強調されている。一見無意味なルールに、落ち着いた諦観で対応する彼の姿は、この世界が、システムがいかに不条理であっても、個人がシステムに立ち向かうことはほとんど不可能であることを伝えている。
ファレルは、サッドボイスSFの王者として君臨する地位を確立した。ロブスター』に加え、最近では韓国系アメリカ人監督カゴナダの『アフター・ヤン』に主演している。ファレルは、美しい企業戦士カイラ(ジョディ・ターナー=スミス)と結婚した茶店の経営者ジェイクを演じている。彼らは、養女のミカ(マレアエマTjandrawidjaja)が彼女の中国の遺産について教えるためにヤン(ジャスティンH.ミン)という名前のアンドロイドを購入しましたが、映画が開くように、ヤンは誤動作しています。彼は何年も家族と一緒に暮らしてきたのに、ミカは寂しくなってしまった。(ジェイクはヤンの修理を試みるが失敗し、ロボットのメモリバンクにアクセスすることができるようになる。ヤンの記憶を見て、彼はこの穏やかなロボットが本当に深い感情を持ち、夢や希望、そして恋心を持っていたことに気づきます。メランコリックで瞑想的、美しい映像。また、明らかに地味である。ジェイクは、ヤンを治すのにどれだけ時間を費やしているか、カイラと口論になるが、彼らの意見の相違は、小声よりも大きな声を上げると電気ショックを受けるかのように、不思議と穏やかなままである。
映画の中の会話はすべてこのように静まり返っている。カゴナダの未来像には、ある種の大量処方の鎮静剤が働いているのではないかと思う。もちろん、そこがポイントだ。悲しい声は、疎外と解離を推論するためのチートコードなのである。(参照)。ホアキン・フェニックスが2013年の『Her』の冒頭で演じたもやもやしたセオドアや、カズオ・イシグロの『Never Let Me Go』を2010年に映画化した際のキャリー・マリガンの穏やかなキャシーのナレーションは、「悲しい声」のSF作品における初期の作品である)。このように、サッドボイスは「抑圧されたキャラクター」を見ているということを観客に効率よく伝えることができるので、これが監督にアピールする理由は簡単です。しかし、『アフター・ヤン』は素敵な映画だが、壁一面のささやき声は別の副作用がある。それは、聴覚的なノボカインのように作用し、プロットの最も繊細な部分であるはずの感情的な衝撃を観客に麻痺させてしまうのである。
これは、悲しい声のリスクである。その高いマナー性は、登場人物の自分自身からの疎外感を伝えるだけでなく、物語と観客の間に距離を置き、映画の感情的な共鳴を奪ってしまうのです。また、ディストピア世界を舞台にした最近の映画『デュアル』では、サラという女性(カレン・ギラン)が、自分が末期的な病気であることを知った後、自分のクローンを作成する。しかし、そのクローン(これもギランが演じており、「サラの複製」と呼ばれている)は、「元の」サラに決闘を申し込むことができる法律を持ち出す。さらに悪いことに、サラのボーイフレンドは彼女のクローンのために彼女を捨て、彼女自身の母親でさえ、ダブルの会社を好むようです。サラは、より好感の持てるドッペルゲンガーを破壊するために訓練しなければならないと決心する。
理屈の上では、心を打つ物語だ。しかし、その実行は直感的に耳障りである。どちらのサラも強烈に腹立たしいので、視聴者は、単にそれを乗り越えて、お互いを殺したら、そんな悲劇にはならないかもしれないと思っても、言い訳にならないだろう。 " なぜ、私は泣いていないのですか? 「と、死んだような目をして上唇をこわばらせながら、医者に尋ねる。サラのクローンはもう少し元気だが、同じようにぎこちない。このように、「オリジナル」と同じように不自然に聞こえることが、サラがいかに人間から切り離されているかを浮き彫りにしている。
ロブスター』と同様、不条理な状況をサラがドライに受け止めることで、より不条理な状況を作り出している。好評を博した『デュアル』は、一部の批評家によりランティモス作品と比較されることがある。これは、ランティモスに対する侮辱です。彼の作品には不快感や嫌悪感さえ覚えることがあるが(『聖なる鹿殺し』をもう一度見るためにお金を払うことはできないだろう)、様式化されたダイアログを含む奇抜さは、一貫したビジョンに奉仕するものだ。しかし、『Dual』ではそうではない。離人症それ自体がキャラクターを面白くするわけでもなく、抑圧だけで世界に説得力を持たせるわけでもない。悲しい声が下手だと、せっかくのSFも一本調子で退屈なものになってしまう。