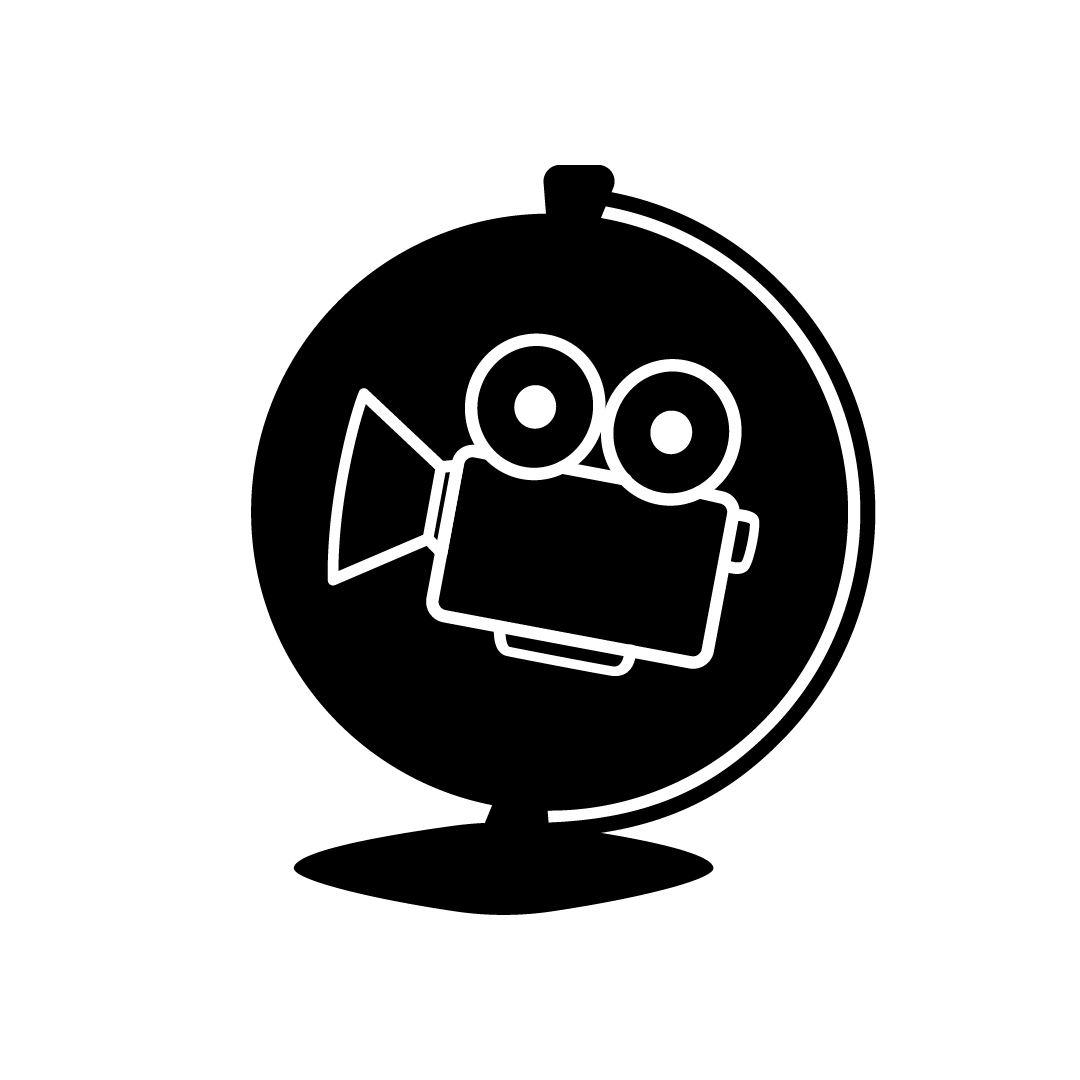Encanto, Disney ' s latest animated musical, would ' ve been a perfect little movie, had two pressure not been exerted on it. 第一は、ハッピーエンドにしなければならないという圧力である。ハッピーエンドは受け入れられる。ハッピーエンドとは、最後の瞬間に、あらゆる失望や不公平や後悔が、まるで魔法でも使ったかのように(文字通りではないにしても)打ち消されてしまうもので、観客がずっと座っていようと準備していた美しく痛ましい感情と一緒に座る機会を奪ってしまうもので、決して許されないものである。残念なことに、アメリカのアニメでは、最も幸せな終わり方をしなければならないという圧力があまりにも徹底しているので、21世紀の今、それに文句を言うのは、弱虫で不条理な感じがするのである。それよりも、『エンカント』のような、あまり語られることのない2つ目の圧力、つまり、魔法を失ったコロンビアの家族の物語が直面する圧力、特に登場人物にかかる「踊れ」という圧力を批判する方が、はるかに洗練されていると私は思うのである。
そう、ダンスだ。音楽に合わせて体を動かすのである。マドリガル姉妹の一人であるルイザは、エンカントで最も人気のある曲「Surface Pressure」で、家族全員のために強くならなければならないというプレッシャーについて歌っている。ルイサは超能力者であり、またリン=マニュエル・ミランダは繊細な作詞家ではないので、彼女は肉体的にも感情的にもこのことを意味する。このように、ルイザは、"圧力 "と "力 "を表現しています。 「この大柄な大人の女性は、ベッドルームの鏡の前で、熱心な子供たちのようにポップアップとロックを繰り返しているのです。「これは、TikTokのダンスのように見える、" 私たちは見ていたように友人が私に言った。その日の夜、彼女は私にTikTokを送ってきた - 本物のティーンエイジャーが同じ踊りを披露しているのだ。
もちろん、このシーンの企画段階で、ディズニーがまさに望んでいたことだったのだろう。悲しき大女優にセクシーなボディロールを見せ、耳障りなセラピー用語に設定し、無料パブリシティが押し寄せるのを見守る。どのような状況であっても下品ですが、アニメーションのエンターテイメントの文脈では?それは一種の嫌悪感です。
主要な芸術の中で、ダンスは実際の力を必要とする唯一のものです。実際、その魅力のすべては、人間の身体の歪み、汗、リスク、勝利の上に成り立っているのです。あの動きは何だろう?あの動きは何だろう、どうやったらあんなに曲がるのだろう。リズムが狂わないか?実写ミュージカルの登場人物は常に踊っていますし、そうあるべきなのです。コンピューターで作られたアニメも自由に踊ることができるが、その際、人工的な動きや、ダンスする理由(diegetic or otherwise)を過剰に意識してしまう。その動きがソーシャルメディア戦略のためにあるような場合はなおさらだ。ディップやスウィーベルは、過剰にプログラムされ、不気味に感じられ、ピクセルが完璧で不穏な正確さでプリエやピルエットをする。最悪の場合、それはフォームの物理的な性質に対する侮辱です。
だから、見ていて楽しくないんです。それはまた、多くの場合、恥ずかしいです。映画の途中でルイザがダンスを始めたり、マドリガルの姉妹がエンカントのヒット曲「We Don ' t Talk About Bruno」を歌い、体を揺らしたりすると、観客がこれらの動きを自分たちのものとして取り入れることを望むだけでなく、長年にわたってアニメーションというジャンルを放棄してきたディズニーの姿勢を感じ取ることができるだろう。エンカント』のような作品は、もはや孤立して存在することはできず、氷上のショーやテーマパークの乗り物から、最も恥知らずなブロードウェイ・ミュージカルまで、あらゆる種類のクロスオーバーの可能性を追求しなければならないのである。
Frozenのせいだ。2013年に公開される以前は、ブロードウェイミュージカルとディズニーミュージカルの違いは少なくとも議論の余地がありました。確かに、『ライオンキング』『美女と野獣』『リトルマーメイド』といった名作は、クオリティの高い順にブロードウェイで上演されてきましたが、どれも劇場公開を前提に作られたものではありません。ひとつには、乱暴なダンスはほとんどなく、もうひとつは、歌はもっと控えめで、派手さはない。しかし、『レント』や『ウィキッド』の重力に逆らうような歌声を持つイディナ・メンゼルが『フローズン』に出演し、ディズニーが本格的なショーチューンの時代に突入すると、その状況は一変した。それ以来、モアナ、ココ、フローズンII、そして今回のエンカントなどの映画は、アニメーションのようなものではなく、舞台作品のように感じられ、文字通り舞台化される準備が整っている。2018年、『Frozen』はブロードウェイでデビューしました。このショーは、苦境にある業界に新しい若い観客を引きつけるのだろうか?おそらくそうだろう。それは、プラットフォームにとらわれないIPのウロボロスが、芸術性の希望を越えて私たちのエンターテインメントを均質化し、表面化することを正当化する十分な理由でしょうか?おそらく、そうではないでしょう。
もしすべてのものが他の何かに作り替えられるように作られているとしたら、何もそれ自体であることに秀でることはできない-それが私たちの時代の物語です。エンカント』には大きな可能性があった。その中には、遺産と再生についての奇跡的で繊細な映画がある。しかし、それ以上でもそれ以下でもないという企業の圧力によって、悲しいかな飲み込まれてしまった。現代におけるディズニー・アニメーションは、目的ではなく手段であり、それは、混乱した多感な観客に対して行われた、テルプシコール的トラウマのような、同期していない、触れてはいけない瞬間から始まるのだ。安全なものは何もない、エンディングでさえも。考えてみてください。アニメは歌に彼らのデジタルブーツを振るために必要とされていなかった場合、そこに 'dは幸せな永遠の後に出て行くにはあまり圧力をかける。実際の感情を感じて、文字が約踊るために何かを持っていないでしょう。